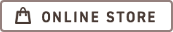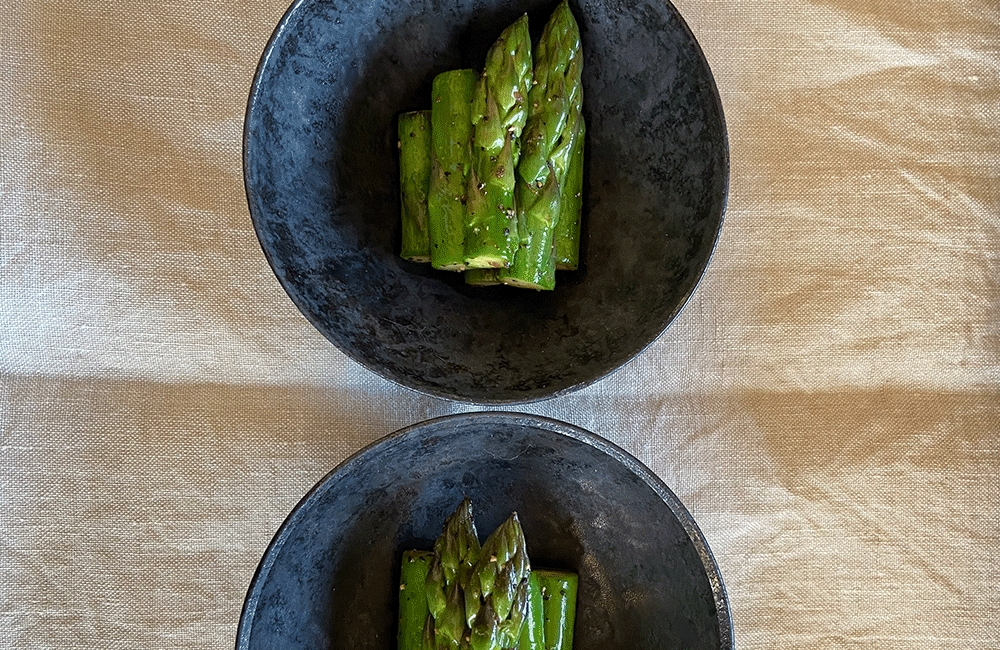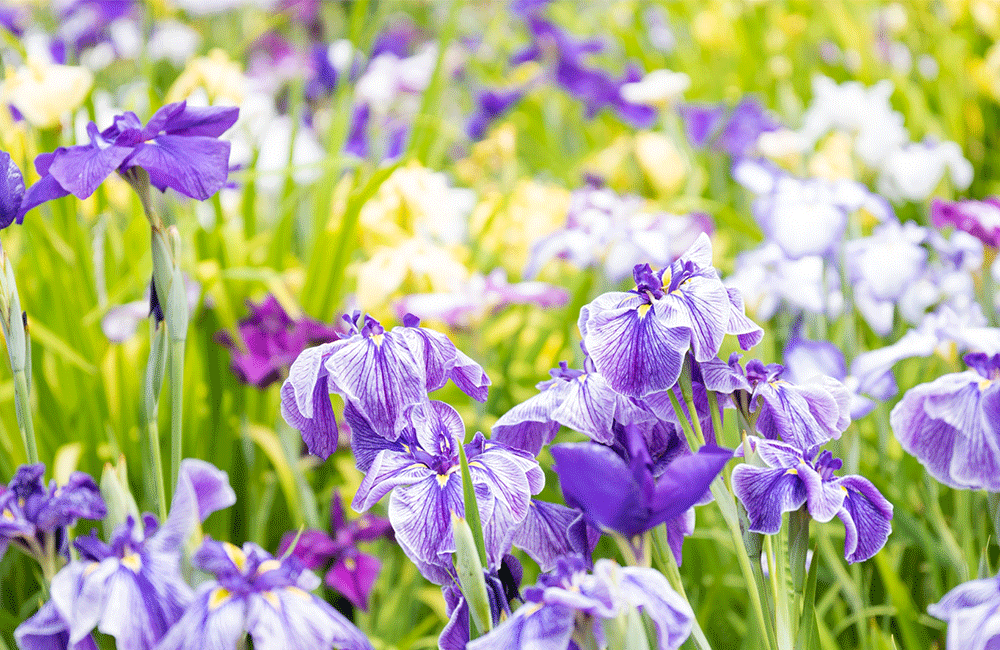すでに日の入りは少しずつ早くなり、夕焼けに明日を想う時間が長くなり、気づくと秋の気配です。二十四節気は、暑さが徐々に和らぐ頃とされる、処暑(しょしょ8月23日)を迎えます。七十二候は、色づいた綿の花が枯れた後、割れた実からふんわりと綿が飛び出す頃、綿附開(わたのはなしべひらく8月23日~27日頃)、取り巻く大気全体に次の季節の雰囲気が寄ってくる頃、天地始粛(てんちはじめてさむし8月28日~9月1日頃)、田圃では穀物の穂先がどんどんと重くなり頭を垂れ、豊穣を予感する頃、禾乃登(こくものすなわちみのる9月2日~6日頃)、と続きます。残暑が続く中でも、そこここに秋の気配が忍び寄りその大気の動きと、その大気に促された植物たちの実りの時を迎えようとしている、そんな秋の訪れに気づく候となります。
と、わかっていても、ゴクリっ、といってしまうのが、夏夕暮れのピールです。ミョウガと新ショウガがたっぷりと盛られた冷ややっこをお供に、お気に入りのグラスに入った琥珀色の液体に閉じ込められた気泡の道筋、その小さな粒を目で追えばふんわりと淡雪のような泡に覆われたグラスの淵。行く夏を惜しむ心持ちを切り取ったような景色です。
実は、ビールホップも今が旬なのです。ビールに香りと苦みをつける役割がある植物、ホップの収穫期は8月前後で、日本では東北や北海道などの寒冷地で栽培されています。時間の経過とともに水分が蒸発すると、香りの成分も弱くなってしまうので、収穫後なるべく早く醸造に使われることが望ましいのです。ビールの醸造は1ヶ月ほどかかるので、ホップ収穫後、8月終わりから9月にかけて国産ホップを使った新鮮なビールが出回るのです。出会えるといいですね。今年の新鮮ビール。
そして、ビール片手に夏を見送る景色と言えば、花火でしょう。江戸時代に隅田川の水神祭で慰霊と悪疫退散のために打ち上げ花火が上げられたのが、現在日本各地で開催される花火大会始まりとされ、夏の風物詩の一つとして、定着しています。最近は音楽に合わせて大きな仕掛けの花火ショーが主流ですが、1950年ごろから日本の花火職人の技術と工夫により独自に発展したものです。
1748年に締結された「アーヘンの和約」(オーストリア継承戦争の終結)を祝うため、イギリス王室ジョージ2世企画の王室主催祝賀イベントにおける花火大会のための音楽として作曲され、初演は翌年、ロンドン市内の公園でした。
この作品は祝典の華やかさを音楽で表現した、序曲(Ouverture)、ブーレ(Bourrée)、平和(La Paix)、歓喜(La Réjouissance)、メヌエット(Minuet)、の5つの楽章からなる組曲です。それぞれが異なる性格を持ち、全体として壮麗な雰囲気を表現しています。序曲のワクワク感、ブーレの躍動感、平和の穏やかさ、歓喜の快活さ、メヌエットの滑らかな舞踊曲、と、いかにも王室らしい華やかさと荘厳さを併せ持ち、どんな花火だったのかを想像しながら聴くのは面白いものです。宗教的な荘厳さと世俗的な華やかさを併せ持ち、バッハとは異なる“劇的で親しみやすい”バロック音楽として広く親しまれていたヘンデルならではの作品です。

もともと、視覚的に劇的で想像力を刺激する花火のきらめきや炎の揺らぎは、水の表現などと似て、本能的で、音で色彩や動きを表現するには格好の題材です。火は情熱、浄化、破壊、再生など多様な意味を持ち、作曲家の思想や物語性を込めやすい題材であり、さらに、花火は祝典や祭り、祈りなどと結びついており、音楽の要素が加わることで高揚感を演出する役割を果たすのでしょう。
海を越え時も違うのに、花火の景色を想像しながらこの曲を聴くと思い出すのは日本の花火の景色。不思議。これも経験のなせるわざでしょうか。皆様はいかがでしょう?
今日も眠りにつくとき、目覚めるとき、素敵な音が聴こえますように。
みなさま、ぐっすりお休みください。